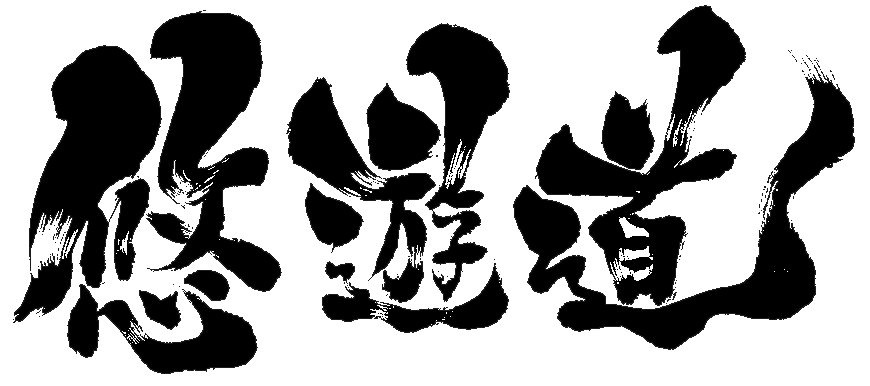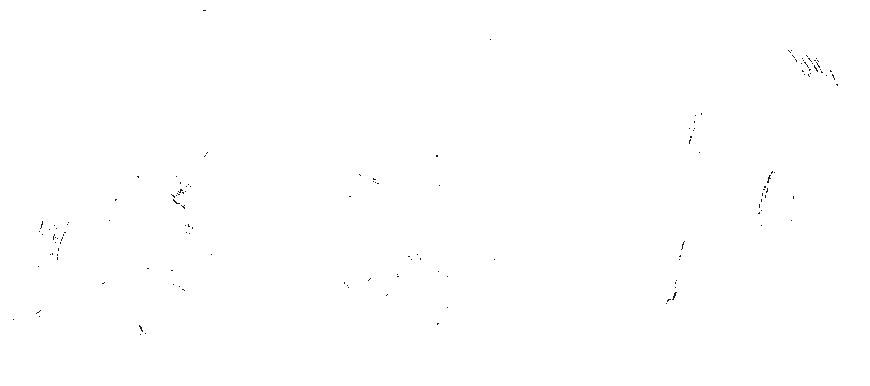白谷さんの家は遠く、こちらの方で開店がある度にポチの家に泊まっていた
見た目はいかつく、縦にも横にも大きいが、人情味があって困った人間がいると放っておくことのできない人だった
泊まる度に、ポチはご飯を馳走になり、いろんな話をしてくれて、つまらないポチの話を聞いてくれた
「白谷さん今度の連休どこか行くんでしたっけ」
「おう、旅行に行くつもりだったんだが、彼女の実家の爺さんの調子が悪いらしいから、取りやめだ」
「面白い爺さんでな、随分良くしてもらったし、顔も久々にみたいから見舞に行ってくるわ」
「ああ、そうなんすか。でも彼女さんもせっかくお休みとれたのにあれですね」
「行く機会はこれが最後じゃねーしな」
「一緒になれば、これから先ずっとすもんね」
白谷さんと彼女さんは婚約しており、互いの親族とも交流があり、両親も認めていて、あとは本人たちが望むタイミングで、となっていた
「ん、だから、俺もそろそろ、まとまった金を作って足を洗わねーとな」
「そうなったら、めでたいっすけど、さみしっすね」
「う、ウソつけコノヤロー!」
「いや、ほんとっすよ。白谷さんの怪獣のようなイビキが聞けなくなると思うと」
「…おまえ、この野郎!!」
彼女のお爺さんの見舞いのことにしても、彼女さんとの結婚もこのままでは出来ないという生真面目な性質もそうだし、ポチが自業自得で誰かから叩かれそうなときも、あまりにも深く入り込んだ話を聞いてしまったために、もう放っておくことが出来ないのである
そもそも、繊細なこの人は、ポチを店の裏で泣かせた瞬間から、ポチのことを本気で怒れなくなってしまっていた
聡明で、人望があり、逞しく、そして優しい
ポチは、こんな兄がいたらいいなと、本気で親愛の情を寄せていた
しかし、ゴキブリのように下水道を這いずり回って生きてきたポチは、太陽のようなこの人と一緒にいることによって、浮き彫りになってしまう自分の浅ましさに、次第に耐え難い恥辱を感じるようになる
ふとした拍子にあらわれる、この人の生まれや育ちのよさはポチを困惑させ、ふとした拍子にあらわれる賤民の出のポチの仕種に、白谷さんは戸惑った
ポチを気遣う気持から、その戸惑いの表情は本当に瞬間ではあったが、その一瞬間の姿が、卑屈なポチの心を搔きむしった
知れば知るほど、この人の打算のかけらもない優しさに、ぽちは魅了されてゆき、そして依存の度合いが色濃くなるにつれて、そこに、妬みやひがみの気持ちが混在するようになっていった
そうした心情は、これくらいは甘えてもいいだろう、これくらいの苦労は掛けてもいいだろうという、攻撃的な気持をポチに芽生えさせる
いつものように、泊っていいかと連絡をくれる白谷さんに、何の理由もないくせに、「ダメです」と拒絶感を全面に出して、断ることが増えてくる
「あ、ああ、そうか」と、平静を装いつつ動揺を見せる白谷さんを眺めては、得体のしれない不気味な何かが腹の底から湧きあがり、しびれるような感覚がポチを包んだ
そのくせ、いい開店があるときには、これでもかと白谷さんにくっついて歩き、他の会の人の批判を買っては、火消しに白谷さんがバタバタと動いていた
ポチは、自身の愚かで未熟で低能なことを「免罪符」のように感じ、白谷さんに甘え切っていた